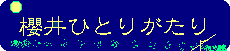眠れない墓
THE UNQUIET GRAVE
(二)
男は大手商社の文書課長だった。これ以上大きな出世は望めないポストと言えよう。だが男には不満も落胆も無かった。わずらわしい人づきあいは少ないし、ほとんど毎日、定時に退社できる。彼は、この仕事が性分に合うと思っていた。
男は会社でも夢見心地だった。仕事そっちのけで(と言っても、たいして仕事は無いのだが)昨夜の出来事を思い返していた。
――現実か、幻か。あの草の汁は何を物語る? 昨夜、たしかにわたしは西の丘を歩いた。でも、よみがえったはずの若さは一夜限り・・・・・・。夢遊病、わたしは夢遊病かも知れない。
男は、若い女性ばかりの職場を見渡した。彼女等の中で、うだつの上がらぬ上司のロマンスを想像する者がいるだろうか。
――夢でもいい。幻でもいい。もう一度彼女に会いたい。今夜も来ると言っていた。信じよう、信じて待とう。
男は眠らずに待っていた。布団の中、北の窓を見つめて。妻が寝息を立てはじめた。
十一時、まだ来ない。窓から、さあっと涼風が吹き込む。頭の中が冷めてきた。失望が心を染める。
――ばかばかしい、おれはなにを期待してたんだ。まったく大の大人が。
急に眠気がさしてきた。うつらうつらとしはじめた時、昨夜と同じように肩を叩かれた。
「今晩は。いえ、お早ようございます。わたしのお寝坊さん」
女は親しみを込めて呼びかけた。男はたちまち跳ね起きて、その袖にすがりついた。
「来てくれたんだね。ああ、よかった」
「そんな、泣きそうな声をお出しにならないで。わたしは約束を守ります」
「若いかい? 今夜もわたしは若いかい」
「ええ。若く、りりしいお姿をしてらっしゃいます」
男は鏡を見た。昨夜と同じ精悍な顔があった。
「さあ、わたしたち達の場所へまいりましょう」
二人はまた、西の丘に肩を並べて座った。
風景は恋人達を迎えるため時を停め、夜のままで待っていたようだ。
「心配したよ。昨日の君は幻じゃないかって」
「幻があなたの声に答えますか。嘘だとお思いになるのなら、わたしを抱いてお確かめになって」
二人は抱きあい、唇を寄せた。寂しい魂が互いに包みあうような、静かな抱擁だった。おだやかな興奮が、かげろうのごとく丘に揺れた。
「虫達が騒がしい。われわれを冷やかしているのかな」
「澄んだ空気を震わせて、その波紋を楽しんでいるのでしょう。きっと彼らにも伝わっているんですよ、ふたりのよろこびが・・・・・・」
「昨日の歌を聴かせて欲しい。なんという題だい?
これくらい、訊いてもいいだろう」
女は少し考えたが、男のせがむような目にほだされて答えた。
「『眠れない墓』といいますの。子供の頃から大好きでした。わたしの母や祖母も歌っていました。いまわたしは、この歌に自分の身の上を重ねずにはいられません。わたしにとってもっとも優しく、悲しい歌」
そう言って女は歌い始めた。
歌声は草むらをよぎり、黒い森の遠景に吸い込まれていった。どんなに高価な布団でも得られぬ安らぎに身をまかせ、男は瞼を閉じた。
「心配なさらないで。北の窓さえ開けておいて下されば、わたしは必ずまいります」
男は安心して眠りにおちた。
最初の出会いから二週間が経った。
二人の逢引は休むことなくつづいた。別れ際、女は「いっしょに来て欲しい」とぐずるようになった。
「どこへ行くんだい」
「二人がいつでも、いっしょにいられる場所へ」
女の返事は明確でなかった。
「それは無理だよ。わたしには仕事があるし、妻をひとりにはできない」
男がそう答えると、女はさめざめと泣き伏した。それから、祈るような表情であの歌をうたい、またいずこへともなく去っていくのだった。
さらに二人の関係が深まるにつれ、男に著しい変化が起きた。
妻との会話が減った。生活に必要な事しか家で話さない。はじめは一生懸命、男の機嫌を取っていた妻も、しだいにその努力を放棄した。子供のいない夫婦にとって、会話の無い家は寝食の箱でしかなくなった。
それにもまして大きかったのは、男の体力の衰えだった。夜ごとよみがえる若さにひきかえ、昼間のだるさはひどくなる一方だった。目はどうにか半開き、まるで鉛の血が流れているかのように手足が重い。勤めを終えて家にたどりつく頃には、這うも同然のありさまだった。
ついにある日、男は職場で強いめまいを覚えた。倒れそうな身体を机に凭せてなんとか支えようとしたが、たちまち目の前が真っ暗になって床に崩れた。
ぼやけていた視界が、徐々にくっきりしてきた。妻の顔があった。彼の顔を不安そうな表情で覗き込んでいた。
「ああ、あなた気が付いたのね。だいじょうぶ、だいじょうぶ?」
しばらく男はベッドのうえで視線をめぐらした。そのうちに、そこが病院の診察室であることに気がついた。
「わたしはいったい」
「会社で倒れ、救急車で運ばれたのよ。連絡を受けた時は、わたしもいっしゅん気が遠のいたわ。でもよかった。気が付いて、ほんとによかった・・・・・・」
妻は男の手を握り締め、人目もはばからず泣いた。
「こら、泣くな。みんなが見てるぞ」
「だって、あなたに何かあったら、わたしはひとりぼっち」
「安心しなさい。わたしはだいじょうぶだ」
男は妻の頭をやさしく撫でた。
「あとは家でゆっくり休んでください。それと、来週早々にでも精密検査を受けた方がいいでしょう。心臓にかなり負担がかかっている。ただの疲労と、なめてかかるとえらいことになりますよ。しんどいと思ったら会社も休む。しっかり眠って、気楽に過ごすことが一番の薬です」
医師はそう言って診察を終えた。
点滴が済むと、夫婦はタクシーで家に帰った。
軽い夕食を済まし、男はすぐ寝床に入った。
「ごめんなさいね。あなたが口をきいてくれないのは、身体が辛かったせいなのね。わたしは、てっきり嫌われたのかと思ってました」
洋服にアイロンを当てながら、妻は男に詫びた。
「実を言うとわたし、さいきん同じ夢をみるんです。あなたが他の女の人と抱き合っている夢。・・・・・・おかしいですね、いもしない浮気相手に嫉妬して。でも本当に悲しかったんですよ」
男はぎくりとした。
「変な話したらいけませんね。今夜は冷えそうだから窓は閉めときますよ」
妻は立ち上がり、北の窓を閉じた。
「開けておいてくれ」男は言いたかったが、それではまた彼女を裏切ることになる。
――今夜くらいは会わずにおこう。せめて今夜は。
男は女への恋しさを抑え、瞼を閉じた。
夜が更けた。外は激しい雨が降っていた。男はぐっすり眠っていた。
女がいつも現れる時間になった。空白となっていた男の脳裏に夢がしのびこんだ。
闇を背景に青白い炎が燃えていた。炎は、自分の通り道をさぐるように宙をさまよう。やがて行く手がふさがれていることを悟ったのだろう、狂おしげに揺れながら地に舞い降りた。
「ああ、約束をお忘れになったのですか。それとも、わたしを拒んでいらしゃるのですか。なぜ窓を閉ざしたのです。わたしにはガラスを砕く力も無ければ、鍵を外す術もない。どうか、いつものようにここを開けてください」
悔しさに満ちた声がただよう。
「わかった、奥さんですね。奥さんが、わたしのことをお気づきになったのね。ああ、憎らしい。わたしは雨に濡れこごえているのに、ひどい仕打ちをした当人は、あなたの隣であたたかくやすらいでいる」
「ちがう、妻は関係ない」
男は炎に向かい叫んだが、相手はまったく聴き入れる様子も無い。
「今夜はあきらめます。でも明日は必ず会ってくださいますね。もし、明日の晩も拒まれるなら、わたし、奥さんを」
「妻をどうする気だ? おい、まて。答えるんだ」
男の呼びかけにはかまわず、炎は彼方へ去るように小さくなって消えた。
そこで夢は途切れた。
「昨夜はすごく、うなされていましたね。悪い夢でも見たんですか」
朝食のテーブルにつくと妻が訊ねた。
どうやら、あれは単なる悪夢ではあるまいと男は直感した。
「おまえの夢に出てくる浮気相手に迫られてね。たいへんだったよ」
「わたしが夢の中まで怒鳴り込めば良かったですね。でも、この話なかなかおもしろいわ。絵を考えるうえでのヒントになりそう」
「おいおい、止めてくれよ。そんなもの部屋に飾られたら落ち着かないよ」
「イメージですよ、それそのものじゃなくて。芸術には、現実を超えたイメージが必要なんです」
男は妻との会話の中で、ふと気付いた。
――そう言えば彼女、どこかで見たことがある。・・・・・・そうだ、美術館だ。あの絵に描かれていた少女にそっくりだ。たしか『眠らぬジューン』という題名、彼女がうたう歌も『眠れない墓』、偶然にしてはどこかできすぎている。
「ねえ、今日は会社を休むんでしょ。ゆっくり寝ていてくださいな。家の中が片づいたら、わたしはあっちの部屋で絵を画いてますから」
「ああ、でも夕方に出かけないといけない。大阪に転勤した同僚が、出張でこちらに来る。六時に会う約束をしてあるんだ」
「その身体で? 断れないんですか」
「もう遅いよ。彼も向こうを発った頃で、連絡がとれない」
「それじゃ、事情をお話して早めにご無礼させてもらったら。それでなくても、あなた、お酒のつき合いで引っ張りまわされやすい人ですもの」
「なるべく、そうするよ。・・・・・・ところで、この間の展覧会の図録を貸してもらえないか。昼間から布団の中にいても退屈だから」
「あらまあ、これまたどういう風の吹きまわしかしら。あなたが、自分からすすんで絵をご覧になるなんて」
「ただ文字を読みたくないだけだよ」
「なるほど、納得しました」
男は図録を持って布団に入った。
さっそくあの絵が載るページを開いた。少女は、やはりジューンにそっくり・・・・いや、ジューンそのものだ。蒼白く澄んだ頬の色から、滝の流れのような衣装の襞まで。じっと見つめていると、いまにもあの歌を歌い出しそうな気がする。
震える手でページをめくり、後半の解説を読んだ。そこに書かれていた作者の略歴も、作品同様不思議に充ちたものだった。
『画家は、この絵を描きあげてから殺人の罪によって捕らえられ、終身刑に処された。だが、まもなく獄中にて発狂、移送先の精神病院で数年後に病没した。その後約一世紀にわたり、彼はイギリス絵画史から抹殺された存在であった――』
固唾を呑んで図録を閉じたあと、天井を見つめて男は考えた。
――やはり『眠れない墓』、あの歌に手掛かりがありそうだ。歌詞や由来を調べれば、決定的な手がかりがつかめるに違いない。『彼』なら音楽に詳しい。妻にはまた嘘をつくことになるが、夜になったら彼の店を訪ねてみよう。
三章へ
|